『詩の生まれる場所』 竹村正人 第7回 学校
朝鮮人にとって学校はまさに「解放」そのものであった
―――鄭栄桓
韓流ブームに肖って昨年末から『朝鮮新報』をとっている。2月23日の紙面には、川崎朝鮮初級学校を訪れた日本の学生らの感想文が載っていた。立命館の院生が記した「否定しようもない美しさ」という言葉が、この記事の大見出しになっている。この言葉、例えば映画『ウリハッキョ』を観た人なら共感できるかもしれない。古びた校舎から溢れ出るアウラの源とは一体なにか。
鍵はチマ・チョゴリにありそうだ。2006年に出版された韓東賢『チマ・チョゴリ制服の民族誌』によれば、チマ・チョゴリ制服はもともと学校の制度ではなく、女性徒たちの自発的な着用によって始まったそうだ。朝鮮学校とはおそらく、この女性徒たちのような無数の構成的な力に支えられている。日本学校に通うことが切実な「選択」としてある時、朝鮮学校への通学路はあまりにも険しいはずだ。その道を歩むという主体的な一歩なしに成立しないのが「ウリハッキョ(私たちの学校)」という名詞の内実なのだろう。
1948年4月、ふきすさぶ嵐の中、許南麒が読み上げた「これが おれたちの学校だ」という詩は、形を変えて歌い継がれているという。最後の一行が日本語になっているのがミソである。
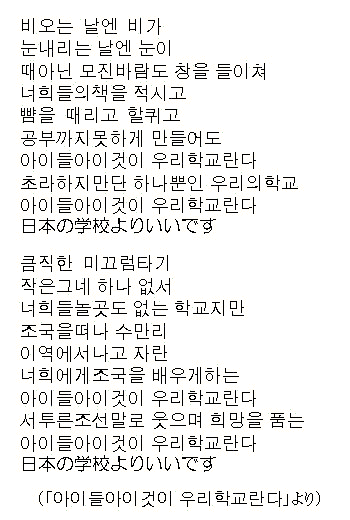
* 冒頭は鄭栄桓「『解放』後在日朝鮮人運動における活動家層の形成と展開」(一橋大学大学院社会学研究科修士論文、2005年)より引用、
文末はネットを参考にしたが、間違いがあるかもしれない。

Trackback URL
Comment & Trackback
Comment feed
Comment